-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
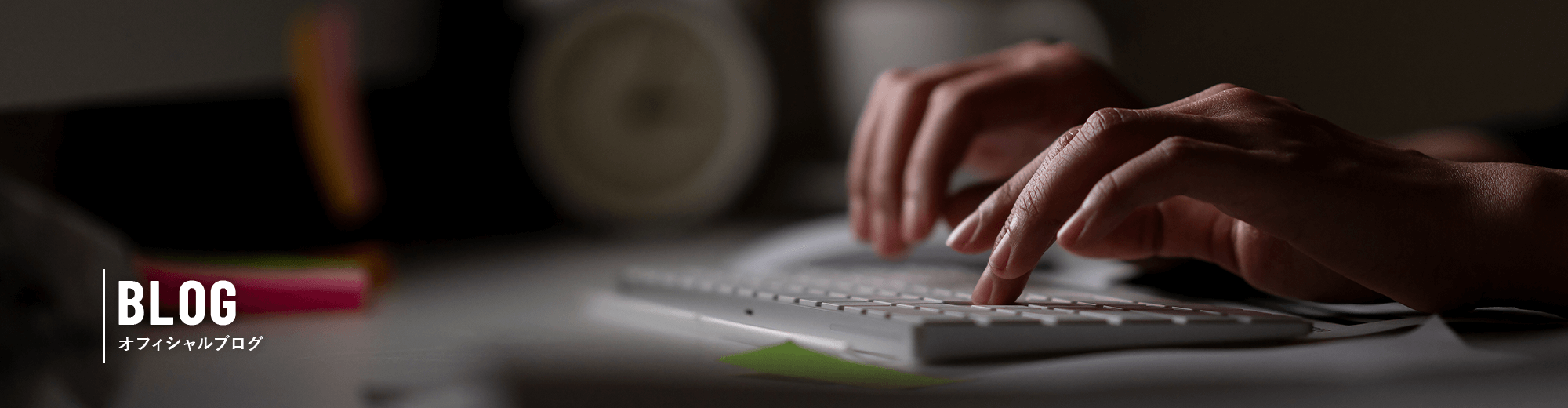
皆さんこんにちは!
井上工業株式会社、更新担当の中西です。
はじめに:基礎は“見えなくなる最高の品質”
プラントの寿命は、地面より下で決まると言っても過言ではありません。測量基準点(BM)の取り方、地盤改良の要否判断、杭種選定、配筋精度、コンクリートの打設・養生、アンカーボルトの芯出し、地下ピットの止水……いずれも竣工後は見えなくなるため、エビデンス(証拠)でしか品質を証明できません。だからこそ、写真・動画・実測値・試験成績・3D点群をその場で残す運用を“標準”にします。
1)測量と基準づくり:誰が測っても同じ値にする
• BM(Bench Mark)冗長化:工区ごとに2点以上のBMを設け、沈下や破損に備えて後背BM(敷地外既設)も設定。豪雨後・地震後の確認ルーチンを作成します。
• 座標管理:設計3Dモデルの座標系と現地の測量座標をトータルステーションで整合。測点は“目印”ではなく数値で共有(XYH)。
• 施工基準線:基礎天端、アンカー芯、機器中心、ラック通り芯を色分けで現地表示。夜間でも読める反射テープ併用。
2)地盤・基礎:支持層に仕事をさせる
• 地耐力の読み方:ボーリング、N値、土質(粘性土・砂質土)、地下水位、液状化。必要なら表層改良・深層混合・置換を組み合わせて、不同沈下の許容差(通り芯±5mm、レベル±3mm など)を初期設定。
• 杭・基礎形式:既製コンクリート杭、場所打杭、鋼管杭、表層改良+直接基礎。周辺騒音や振動規制、搬入制限を考慮して選定。杭頭処理のかぶり厚・鉄筋定着は写真で全数記録。
• アンカーボルトの基礎内固定:鋼製テンプレートで位置決めし、曲げ・傾きをゲージで確認。テンプレートは識別タグを付け、型枠解体まで外さない。
3)配筋・型枠・コンクリート:打設前の5分で未来を守る
• 配筋:鉄筋径、ピッチ、定着長、あき。スペーサー種別と数量、かぶり厚(基礎=一般的に60mm以上など)を型枠閉じ前に写真撮影。重ね継手の位置ズレ(ずらし)を図示。
• 型枠:通り・レベル・対角寸法を対角測定で検証。漏水を防ぐ目地処理、止水材位置をチョーク+写真で残す。
• 打設計画:スランプ・空気量・温度・配合を事前に確定。ポンプ車の配置、バイブレータ本数、打設区分、ジョイント位置、打設順序、コールドジョイントの回避手順を朝礼で共有。
• 養生:初期養生(湿潤・保温)、高温期は打設時間を前倒し、低温期は保温養生+防凍剤。温度計埋設で温度ひび割れ解析の根拠を残す。
4)アンカーボルト・グラウト:据付精度の土台をつくる
• アンカー実測:芯間、対角、露出長、ネジ山状態。レベルは水準計+レーザーで二重確認。許容差を機器仕様から逆算して設定。
• グラウト:無収縮モルタル/樹脂系の選定。基礎目荒らし→レイタンス除去→湿潤化→片側注入→エア抜き→規定強度まで無荷重。座金はリフトアップ法で撤去するか、残すなら位置を図示。
5)地下ピット・埋設配管・排水:水と腐食をコントロール
• 止水:コールドジョイント、貫通部の止水板・止水材。貫通スリーブは将来増設分の盲スリーブも設置。
• 排水計画:油水分離、雨水・汚水系統分離、逆勾配の未然防止。グレーチングは荷重等級を明記。
• 防食:地下配管は被覆、犠牲陽極、テープ巻き。地中での異種金属接触を避ける絶縁継手。⚡
6)品質管理と記録の作法
• 試験体:圧縮強度、曲げ、促進中性化。打設ロットごとに採取し、温度履歴と紐付け。
• 出来形検査:レベル・通り・対角・開口。点群スキャンでAs-Built化し、埋設物位置図を作図。
• 引継資料:アンカー実測、埋設管・電気管の位置台帳、止水材の種類・位置、写真台帳、強度試験成績、温度履歴、コア採取位置。
7)よくある失敗と処方箋
• アンカー芯ズレ:テンプレート固定不足→斜め引張で再施工。是正はケミカルアンカー+構造計算で担保。
• ジャンカ・豆板:バイブ不足/打設順序不良→補修材+断面修復、防食塗でカバー。原因を再発防止会で共有。
• 逆勾配の排水:レベル基準の参照ミス→排水テストを型枠解体前に実施。
8)チェックリスト(抜粋)✅
☐ BM・座標の冗長化と日次確認
☐ 地盤・液状化評価、改良要否、杭種決定
☐ 配筋写真(径・ピッチ・定着・スペーサ)/型枠対角
☐ コンクリ配合・温度・スランプ・打設順序・養生計画
☐ アンカー実測台帳(XYH・露出長・ねじ山)
☐ ピット止水・貫通部・排水勾配の検査記録
☐ 点群スキャン・埋設台帳・強度試験成績
結語:“1mmの狂いが、10年のコストになる。” 地下の品質は書類でしか語れません。今の一手で未来を軽くしましょう。✨